今回は、民法初学者にとっても、つまづきやすい用語である「債権者・債務者」について解説します!
債権と債務の関係性
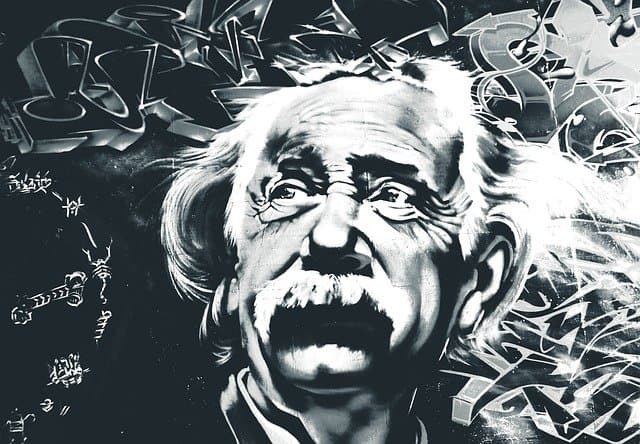
売買契約
例えば、Aさんはノートパソコンをもっていますが、スマホばかりで、ぜんぜん使うことがありません。
でも捨てるのももったいないですよね。(買うときに15万した)
とはいえ持っていても邪魔になるだけです。
ちょうどそのころBさんは、オンライン授業のためノートパソコンが欲しいと思っていました。
スマホでは目が疲れます。
でもお金を1万円しかもっていません。
多少古くてもいいから、誰か1万円でノートパソコンを売ってくれないかなあって思っています。
A→ノートパソコン
B→1万円
もしこの2人がであったらどうなると思いますか?
Aさんはノートパソコンを処分したい。
Bさんはノートパソコンを安く買いたい。
Aさんが「1万でいいよ!」と言えば、Bさん即決で購入することでしょう。
これでAさんBさんの間に売買契約が結ばれたことになります。
A→ノートパソコン→B
B→1万円→A
ここからが問題です。
契約は結ばれましたが、これでゴールではないのです。
Aさんは1万円。
Bさんはノートパソコン。
目的のものが手に入って初めてゴールなのです。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法555条
売買契約が成立すると債権・債務が発生する
民法は売買契約が結ばれると、債券、債務が発生すると定めています。
債権とは、、、ある人がある人に「これして」「これしないで」と要求できる権利です。
債務とは、、、ある人がある人はから「これして」「これしないで」と要求される権利(つまり義務)です。
今回の例で言うなら
| 債権 | 債務 | |
| Aさん | 1万円もらう | ノートパソコンを渡す |
| Bさん | ノートパソコンを貰う | 1万円を払う |
このような関係になるのです。
結論:債権者、債務者の違いとは?
債権者は要求できる人。
債務者は要求される人。
この違いがあります。
しかし、債権者と債務者の関係性は、その目的のものに対する立ち位置で変わります。
Aさんが「1万円を払って」とBさんに言える権利が債権です。
つまりこの視点から見ると
Aさんは債権者。
Bさんは債務者になります。
ところが、Bさんの「ノートパソコンを渡せ!」これも債権なんですよね。
つまりこの視点からだと
Aさんは債務者
Bさんは債権者となります。
とってもわかりにくいですよね。
契約のタイプや、その人の立ち位置や視点によって、債権者か債務者が変わってしまうんです。
債権者、債務者とワードがでたら、必ずどの債権の立ち位置に立って説明されているか確認しながら、民法学びましょう!
 ごり子
ごり子読んでくれてありがとう!
>>【最新版|2022年】公務員試験ランキング!簡単?難しい?難易度を偏差値でランク付け!
★公務員試験対策の目次
【民法】公務員試験対策に使える!おすすめの参考書・過去問
【憲法】独学で憲法が学べるおすすめの参考書10選! 【公務員試験】
【行政法】公務員試験対策の参考書・問題集をおすすめ順に紹介!!【2021年】
【数的推理・判断推理】これやっておけばいい!おすすめ参考書と勉強法を紹介!
クレアールという通信系の予備校が無料で公務員ハンドブックを発行しているので、時間のある方は確認しておきましょう。
試験についてや、合格体験記など幅広く載っています。


コメント