勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
出典:憲法第28条
資本主義において、労働者は弱い立場に置かれがちです。
本条は労働者が使用者(企業側)と可能な限り対等に立ち、よりよい労働環境を享受することを目的としています。
今回はこの28条を解説します。
労働基本権(労働三権)とは?

 ごり
ごり労働三権って権利が3つあるってこと?



そうだね。
労働基本権の内容は、団結権、団体交渉権、団体行動権の3つに分けることができるよ。
だから労働三権て呼ばれるの。



28条に書いてあるやつね。
でもそれじゃあ勤労者って誰?
労働者じゃないの?



労働者と同じだよ。
給料をもらっている人になるかな。
公務員は入るけど、自営業者は入らないよ。
勤労者とは?
28条の言う勤労者は労働者と同じ意味です。
つまり、他人に労働力を提供することで対価である賃金、報酬を得て生活をする人を指します。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
出典元:労働組合法3条
失業者も勤労者?
失業者も労働の対価である賃金で生活することに変わりはありません。
自営業者は勤労者にあたらない
自ら業務を営む人は対象になりません。
例えば、農業や漁業がこれに当たります。
公務員は勤労者にあたる
反対意見もありますが、判例通説では公務員も勤労者として認めています。
団結権とは労働条件改善のため団体を組織する権利





労働条件改善のため団体ってなに?



いわゆる労働組合だね。
団結権は既存の組合に入る、または新しく結成して、その活動に参加できる権利だよ。
団結権とは?
団結権は、労働者が労働条件を維持、改善するための団体などを組織する権利をいいます。
通説では一定の強制加入も認めるとしています。
団結権は一時的な団体も認める
労働組合のような継続団体だけでなく、リストラにあった人がその撤回を求めて組織する争議団のような一時的なものも含むとされます。
団結しない権利
消極的団結権と呼ばれるものです。
通説的見解では、強制加入を否定せず限度があるとし、脱退の自由を奪うことまでは許されないとしています。
組合員であることを義務付けるショップ制
ショップ制は組合員であることと、従業員であることを関連させる制度をいいます。
代表的なものに、クローズド・ショップ、ユニオン・ショップ協定があります。
クローズド・ショップ協定
使用者は、労働組合員しか採用できないとする制度です。
ユニオン・ショップ協定
日本に多い制度です。
採用されると強制的に労働組合に加入しなければならなくなります。
また組合から脱退・除名された者を、使用者は解雇しなければなりません。
三井倉庫港運事件
- ユニオンショップ協定を締結した組合以外の労働組合に加入
- 締結組合から脱退、または除名されたものが、他の労働組合に加入か新たな組合を結成
上記のような場合の解雇義務は、他の組合の団結権も保障されるべきであり、民法90条(公序良俗違反)より無効だとされました。
組合には統制権がある?
労働組合には統制権があり、組合員の違反行動に制裁を行えるとされています。
三井美唄炭鉱労組事件
判決では目的達成のために必要であり、かつ、合理的な範囲において統制権を有するとしています。
本件のように、組合の意にそぐわない市議会議員選挙の立候補をやめないことへの処分は、統制権の限界を超えるものだとされました。
団体交渉権は労働条件について交渉する権利





誰が交渉するの?



基本的には労働組合のような団体を想定しているよ。
団体交渉権とは?
労働者の団体(労働組合に限らず)が、使用者と労働条件の維持改善を交渉する権利です。
交渉の結果、妥結すれば、労働協約という文書にまとめられます。
労働協約
法規的性格を持ち、定められた労働条件に違反する労働契約の部分は無効となります。
契約全てが無効となるわけではありません。
ストライキなどを認める団体行動権(争議権)
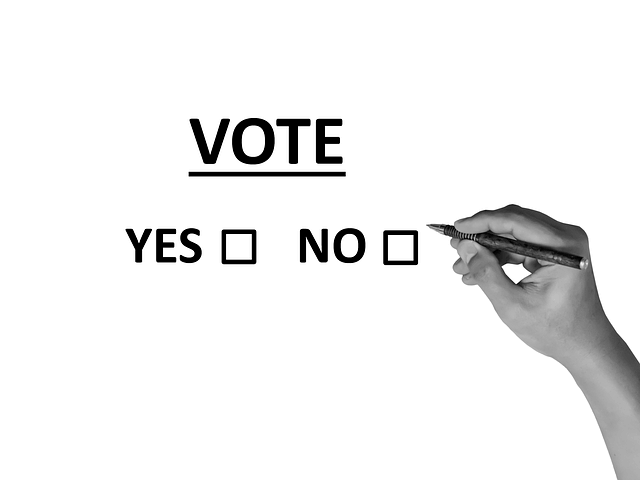
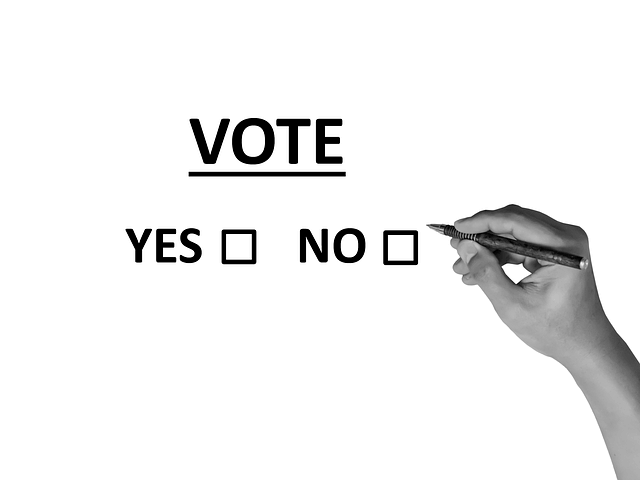



ストライキは何のためにするの?



労働者は1人1人は弱い立場にいるから、何か要求しても簡単に断られてしまったりするの。
だからみんなで仕事を休むことで大きくなって、会社側に対抗するんだよ。
団体行動権とは?
労働者の団体が、労働条件の維持改善のために、使用者に対して争議行為(ストライキなど)を行う権利です。
争議行為
団体交渉を以外の団体行動を争議行為と呼びます。
中核にストライキがあり、他にもそこから生じるいくつかの争議行為があります。
サボタージュ、ロックアウト、生産管理などです。
争議行為の限界
争議行為であれば何をしてもいいわけではありません。
政治スト
労働条件の維持改善が目的ではなく、政治目的に行うストライキです。
判例では28条の保障を受けないとされました。(全農林警職法事件)
生産管理
労働者が工場などの生産手段を支配下におき、使用者の支配から抜け出して、自分たちで企企業経営を行う争議行為です。
判例では28条の保障を受けないとされました。(山田鋼業事件)
制限される公務員の労働基本権
公務員に争議権はない
国民生活への影響力の大きさから、すべての公務員に争議権は認められていません。
国家公務員の争議権を一律に制限することについても、判例で合憲とされました。
労働三権すべてを制限
警察官、消防職員、自衛官、海上保安庁職員は3権すべてが保障されません。
違反した場合、国家公務員、自衛隊に関しては罰則もあります。
非現業公務員は団体交渉に制限
団結権が認められる非現業公務員ですが、その組合は交渉権に制約があり、労働協約の締結権もありません。
現業と非現業の違い
権力行為を行うかどうかの違いです。
現業が公権力を行使しない公務員です。
ただし、学校の用務員やごみ収集作業員が現業で、看護師や保育士が非現業であることから、合理的な区別とまではいえません。
技能労務職されるものを非現業とするともしています。



読んでくれてありがとう!
>>【最新版|2022年】公務員試験ランキング!簡単?難しい?難易度を偏差値でランク付け!
★公務員試験対策の目次
【民法】公務員試験対策に使える!おすすめの参考書・過去問
【憲法】独学で憲法が学べるおすすめの参考書10選! 【公務員試験】
【行政法】公務員試験対策の参考書・問題集をおすすめ順に紹介!!【2021年】
【数的推理・判断推理】これやっておけばいい!おすすめ参考書と勉強法を紹介!
クレアールという通信系の予備校が無料で公務員ハンドブックを発行しているので、時間のある方は確認しておきましょう。
試験についてや、合格体験記など幅広く載っています。


コメント