この記事では、権利能力の始まりと終わりについて解説しています。
権利能力とは、法律上の権利・義務の帰属主体となることができるという一般資格のことをいいます。
また、権利能力を持つ者を権利主体といいます。
簡単に言えば、社会というステージに立つための資格みたいなものです。
普段、物を買ったり、働いたり、学校に行ったり、いろんなことをしてますよね。
これは人に権利能力があるからできるわけです。
よく、ロボットが進化して人間と同じようになれたら、権利をどうするのかという問題定義がありますよね。
その「権利」というのが権利能力にあたります。
帰属主体には、自然人と法人があります。
今回は自然人、つまり人の権利能力の始まりと終わりがメインです。
権利能力の始まり:胎児に権利能力あるのか?
自然人(人間)は出生から、つまり生まれたら権利能力が手に入ります。
次の条文を見てください。
私権の享有は、出生に始まる。
民法3条1項
胎児に権利能力はないのか?
3条1項を逆に考えると、生まれるまでは権利能力はないともいえます。
ただこれを厳密にとらえると、胎児にとっての不利益につながる場合があります。
例えば相続です。
胎児の父親が交通事故で死亡したら
そんなことあったらダメですが、母親が妊娠中に父親が死亡する可能性も0ではありません。
もし、それが交通事故で亡くなったら、、、
本来相続されるはずの加害者に対する損害賠償請求権を失うことになります。
さらに自己固有の慰謝料請求権も、当然取得できません。
たった一日生まれる日が違うだけで、権利が取得できるかできないかが変わってしまいます。
出生擬製とは?
そこで、民法では、3条はそのままに一定の条件の場合には、いったん生まれたとみなすという方法をとります。(出生擬製)
細かい内容は相続で学ぶ内容になります。
ちなみに死産の場合は出生擬製は働きません。
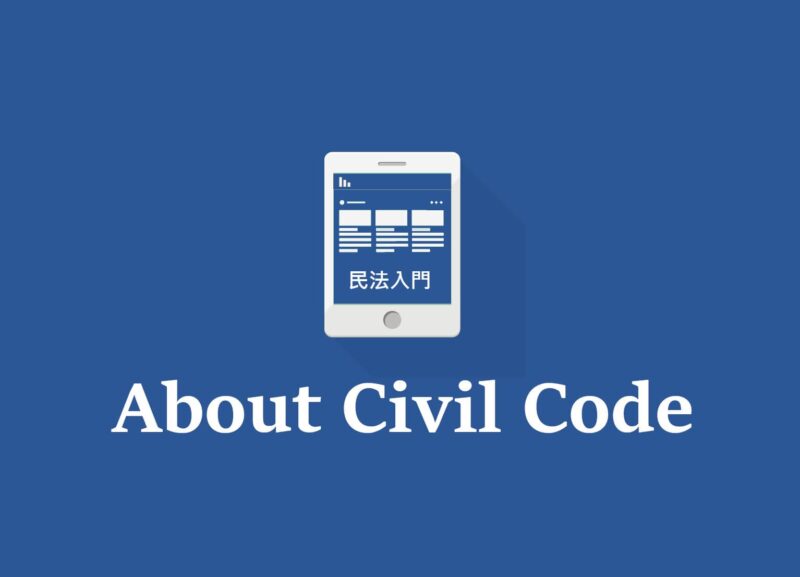
権利能力の終わり
当たり前ですが、権利能力の終期は死亡時です。
基本的には心停止をもって死亡状態としていました。
問題になったのは、医療の発展により生じた、「脳死」の場合です。
「脳死」を死としてよいのか?
臓器移植の広がりも合わさって様々な議論が行われています。
臓器移植法により、脳死は人の死とされた
あくまで一定の要件のもとにですが、脳死の患者からの移植が認められています。
つまり、移植される場合に限り、脳死は人の死とされました。
失踪宣告と死亡擬制
失踪したからといって、死亡したとは限りません。
そのため権利能力を失うわれなはずです。
しかし、それでは家族らに不都合が生じる場合があります。
そこで失踪宣告により、死亡が擬製されます。
これは、利害関係者間での死亡扱いであるので、どこかで生きている失踪者の権利能力が失われるわけではありません。
あくまで、その家族らの救済措置です。(妻が再婚できないとか)
生きていることが分かった場合でも、死亡擬製の効力は失われません。
裁判所に申し出をして初めて取り消せます。
終わりに
相続や家族のところで細かくやる内容です。
軽くでいいと思います。
 ごり子
ごり子読んでくれてありがとう!
>>【最新版|2022年】公務員試験ランキング!簡単?難しい?難易度を偏差値でランク付け!
★公務員試験対策の目次
【民法】公務員試験対策に使える!おすすめの参考書・過去問
【憲法】独学で憲法が学べるおすすめの参考書10選! 【公務員試験】
【行政法】公務員試験対策の参考書・問題集をおすすめ順に紹介!!【2021年】
【数的推理・判断推理】これやっておけばいい!おすすめ参考書と勉強法を紹介!
クレアールという通信系の予備校が無料で公務員ハンドブックを発行しているので、時間のある方は確認しておきましょう。
試験についてや、合格体験記など幅広く載っています。


コメント