教育を受ける権利は、国家に教育制度の整備を求める権利という意味を持ちます。
また国家による自由のため、社会権に分類されます。
今回はこの教育を受ける権利を解説します。
 ごり
ごり具体的にどんな意味があるの?



この権利が保障されているから、義務教育という制度が作られているよ。
皆が平等に教育を受けられるでしょ。



学校って権利だったてこと?
教育を受ける権利とは?


すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
憲法26条
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
どんな意義がある?
教育は、人が人らしく生きるために必要な物です。
そのため憲法25条で保障する生存権の文化的側面だとされます。
子供が学習する権利でもある
判例・通説では、子供の学習権を教育を受ける権利の中心に置くべきだとしています。



人間として、成長して、発達して、自分の人格をつくりあげていくために必要な学習をする権利だよ。
「これを無償とする」ってどこまで無償?
判例では授業料が無償だと解釈されています。
教育権はどこにある?
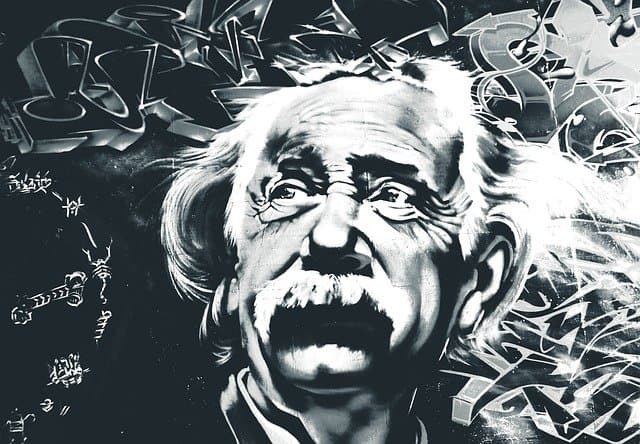
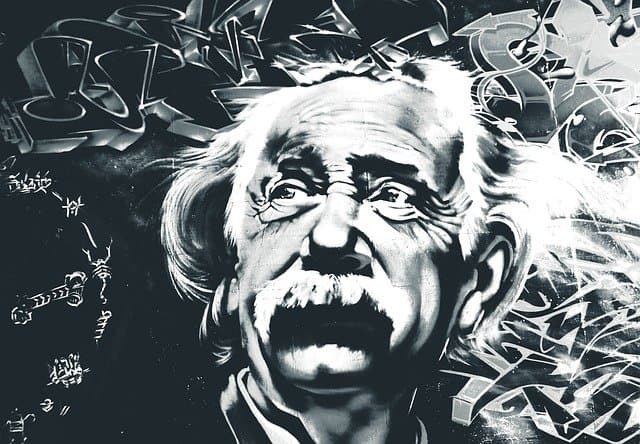
教育とは、知識のあるものがないものに教えるという、非常に一方的な構造になっています。
そのため教育の内容を誰が決めるのかが問題になり(教育権の所在)、これには学説上の対立があります。
国家教育権説
教育といえど、1つの国の政策である以上、国会により決定されるべきだとする説です。
また法律の委任を受けた文科省が作成する学習指導要領は、学校や教師を拘束するとしています。
国民教育権説
親、またその信託を受ける教師を中心とした国民全体が責任を負うとする説です。
最高裁の立場
最高裁は旭川学力テスト事件判決で、どちらの見解も極端で一方的だとし、教師の教授の自由を認めつつも、国に必要かつ相当と認められる範囲において、教育権を認めました。(折衷説)
まとめ
- 教育を受ける権利は子供の学習権
- 義務教育の授業料をとらないことを保障
- 判例では教育権に関して折衷説をとった



読んでくれてありがとう!
>>【最新版|2022年】公務員試験ランキング!簡単?難しい?難易度を偏差値でランク付け!
★公務員試験対策の目次
【民法】公務員試験対策に使える!おすすめの参考書・過去問
【憲法】独学で憲法が学べるおすすめの参考書10選! 【公務員試験】
【行政法】公務員試験対策の参考書・問題集をおすすめ順に紹介!!【2021年】
【数的推理・判断推理】これやっておけばいい!おすすめ参考書と勉強法を紹介!
クレアールという通信系の予備校が無料で公務員ハンドブックを発行しているので、時間のある方は確認しておきましょう。
試験についてや、合格体験記など幅広く載っています。


コメント